伝える力を育てるために―つばめ学院が感想文にこだわる理由
2025年2月28日 Vol.1003
つばめ学院は埼玉県和光市にある「生徒を元気にする塾」です。
塾長の関口です。
つばめ学院ではGWの連休の課題として、小学生に「読書感想文」を提出してもらっています。もちろん、塾での添削もします。何を書いてよいかわからない子に対しては塾長がヒアリングをしながら内容の構成を一緒に考えます。
今日は、その読書感想文の意義について、私の考えをご紹介します。
ご家庭でも『読書感想文なんて嫌だ!』というお子さんに伝えていただける内容です。
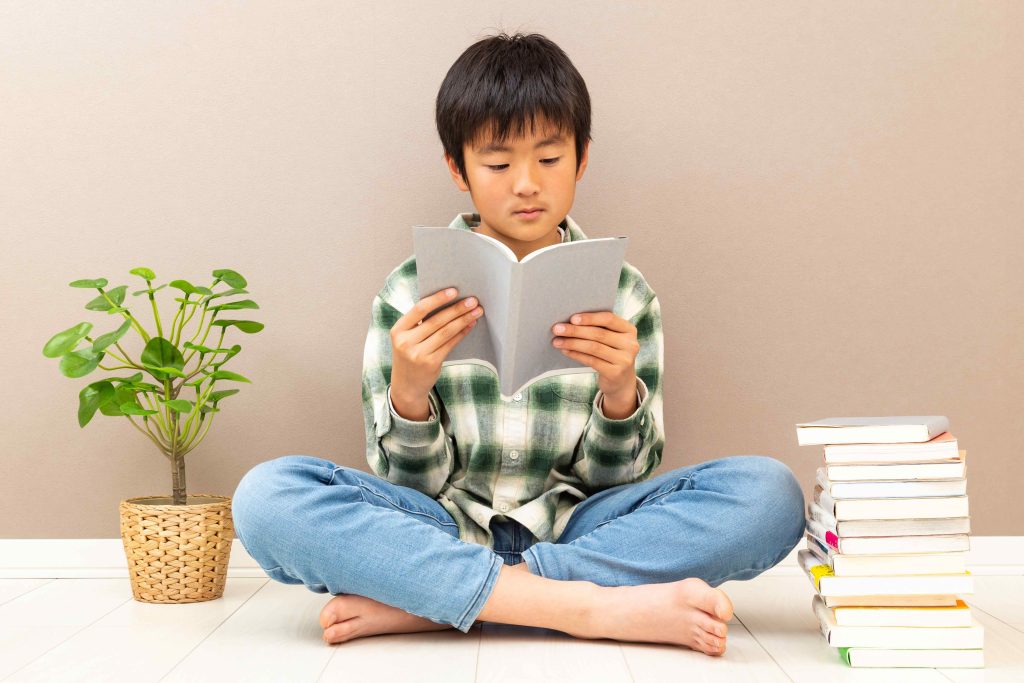
自分の考えを言葉にするということ
生徒たちには「自分が何を感じて、何を考えたのかを言葉にすることは大切だよ」と伝えています。
この『言語化』がなぜ大切かを説明するのは、意外と難しいと感じています。
まずは、「人生は選べる」という本の著者である、勝山恵一さんの言葉をご紹介します。
“ 28歳になったいまの僕を見て、19歳までの荒れていた僕の姿を想像するのは難しいかもしれない。いま敬語も話せるし、ムカッとすることがあっても、殴るのではなく言葉でちゃんと説明することができる。
でも、若い頃の僕は言葉で説明するということがまったくできなかった。いま思えば、自分の気持ちを説明する言葉を知らなかっただけなんだけど、当時の僕はネガティブな感情が芽生えると、その瞬間に手が出ていた。”
勝山さんは、人を殴る要因の一つに「言葉を知らない」ということをあげています。
このことに、ご自身の経験から共感できる保護者は少ない気がするので、別の視点から考えてみようと思います。
感情を「表現」する力
今回は「怒り」の感情について考えます。
これは私自身も経験したことですが、思い切り腹が立ったときに「自分がどう腹が立って、何を考えていたのか」を相手に伝えると気持ちが落ち着きます。
(毎回、ぶちまけてばかりでは困りますが・・・)
私は腹が立った時でも、あまり「きつい言葉」を使ったり、モノにあたったり、ましてや暴力に訴えることはありません。
ただ、それは私の性格なのではなく、単に「適切な言葉を知っているだけ」なのかもしれません。
もし、自分の気持ちを適切に表現できない場合には、相手を傷つけるような言葉を使ったり、机を叩いたりする。そうした表現に頼らざるを得なくなるのかもしれません。
言葉はトラブルを防ぐ手段でもある
インターネットのSNSでは、言葉に関するトラブルが絶えません。
これも表現の問題なのかもしれません。
ある人が日々の生活の中で、自分の気持ちを適切に表現できずストレスをためてしまう。その結果、ふと目にした情報に対し、強い言葉で批判してしまうということは、ありそうな話です。
読書感想文を書くという行為は、
・自分の気持ちを知ること
・自分の気持ちを表現すること
の2つからなります。こうした力は、きっとお子さんを無用なトラブルから守る助けになるはずです。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます。
おわりに、つばめ学院の読書感想文で使う課題図書6冊をご紹介します。連休中の読書の参考にしてください。
1. 「先生、感想文、書けません!」 山本悦子
2. 「くちぶえ番長」 重松清
3. 「ゲド戦記1 影との戦い」 アーシュラ・K・ル=グウィン
4. 「シートン動物記1」 アーネスト=トムソン=シートン
5. 「トモ、僕は元気です」 香坂直
6. 「かなたのif」 村上雅郁
